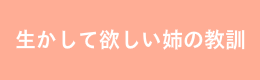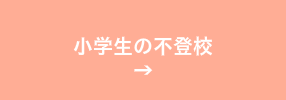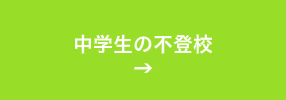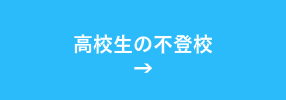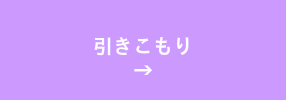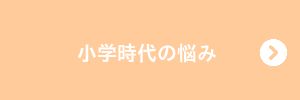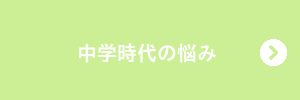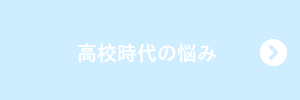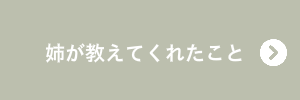褒めて育てる 子育ての注意点

近年、「褒めて育てる」や「怒らない子育て」が主流になりました。
しかし、「褒めて育てたのに、不登校になった」という事例があります。
そこでここでは、「褒め過ぎがよくない理由」と
「褒めて育てる 子育ての注意点」をお伝えします。
目次
1.不登校生の親御さんからのご質問
2.褒め過ぎが良くない理由
3.怒る・叱る・注意する
4.伝える工夫で 子どもが変わる
不登校生の親御さんからのご質問
先日、不登校でお悩みのお母さんから、下記のようなご質問がありました。
【ご質問】
今までずっと、「いっぱい褒めて育てよう!」と子育てを頑張って来ました。
でも、中一の娘が不登校になって…
周囲からは「過保護」や「褒め過ぎ」と言われショックです。
私の褒める子育ては、何がいけなかったのでしょうか?
褒め過ぎがよくない理由

【 アドバイス】
お子さんをたくさん褒めて、子育てを頑張って来られましたね。
近年、「褒めて育てる」や「怒らない子育て」という考え方が、主流になりつつあります。
これらの考え方について、「とてもいい考え方だな」と、私は思っています。
但し、いい面を強調し過ぎる傾向が強いようです。
そのため 多くの人に誤解を招いたまま、伝わってしまったようなのです。
例えば、物事には必ず二面性 や さまざまな側面 が存在します。
分かりやすく言い換えますと、「いい面」と「悪い面」。
「メリット」と「デメリット」。「安全」と「リスク」。
「白」「黒」「グレー」なんて表現もありますね。
物事をどう捉え(考え)、どう活かすのか?
私達は、これらのことを常に考えながら、日々生活しています。
その中で、怒られたり、悪いこと(ネガティブ・不安・リスク)ばかり言い続けられると、気分が沈んだり、やる気がなくなる。
かといって、グレーの まだよく分からない状態は、そのことをずーっと考えていることになるので、しんどい。
それならいっそ、いい面だけを見て「褒めよう!」と決めてしまえば、その他の部分は、考えなくて済む!
同時に、褒められて怒る人は少ないですから、「相手も喜んでるし、自分も楽だし♪」と考えるようになります。
すると、いつの間にか「叱らない」や「都合の悪い事は伝えない」。
あるいは、お子さんのテストの点数が、100点満点中 24点だったにも関わらず、「頑張ったね」なんて…、本音ではそんなこと思ってないのに 言ってしまう。
つまり、「褒める」を意識し過ぎて、「叱ってはいけない」とか、「嫌なことを言わないでおこう!」と思い過ぎてしまったのです。
もちろん、これらの行為は、相手の年齢や内容によっては、「思いやり」や「優しさ」かも知れません。
しかしそこには…
「叱り方が分からない」
「下手なことを言って反発されては、面倒だ」
「機嫌を損ねないように、褒めておけばいいや」
「気遣っているふりをしよう」
このような打算が入っているのではないでしょうか?
このような接し方を、商売(ビジネス)として、割り切っているならともかく、大切な人に、もしあなたがいつもされたら どう思いますか?
おそらく…
「何が本当にいいのか、分らない」
「なんか胡散臭い」
「なんでも いいよかよ!」
「真剣に向き合ってくれない」等と、思いませんか?
すると、本心ではないことを見破られて、「大切に扱われていない気がする」。あるいは、「寂しい」と感じたりするのではないでしょうか?
怒る・叱る・注意する
また、上記でも少し触れましたが、「叱り方が分からない」という親御さんも多くいらっしゃいます。
実は、「怒る・叱る・注意する」では、対応も感情も全く違います。
ここで、簡単にご説明しますね。
◆怒るは、自分(親)の思い通りにならないから、嫌に思うエネルギーを、相手に発散している状態ですね。相手の為ではなく、自分の為に行っている行為です。
◆叱るは、相手の為に「どうしたら聞いてくれるのか?」を冷静に考えて伝えている行為です。相手が聞いてくれる為なら、大袈裟な演技やリアクションを取ってでも、相手に伝わるように伝えていきます。
◆注意するは、相手が主導です。
親が何かを伝えても、それを選択するのは相手に委ねている行為です。
伝える工夫で 子どもが変わる

このように、「褒め過ぎ」や「いい面だけ」を伝えることは、「嘘・方便」が多くなり過ぎてしまい、歪んだり、偏った考え方 を伝えることになります。
すると「寂しさ」や「孤独」を感じさせてしまい、結果的に、裸の王様のような 「現実を正しく見ることのできない大人になる」可能性が高いのです。
ですので親御さんは、 褒めることは大切ですが…
・犯罪
・命の危険に関わること
・明らかに自分を粗末にする行為
・相手を不快にさせることへの注意 等
日常生活で起こる出来事をよく吟味して、お子さんのために、「叱る・注意する」も同時に、心掛けてみて下さい。
加えて、その時の内容、お子さんの年齢に応じて、自尊心を傷つけないよう工夫して伝えることも、忘れてはいけません。
例えば、宿題をやらないお子さんの場合。
「早く、宿題をやりなさい!」と、頭ごなしに怒るのではなく…
宿題に対して やる気を出してくれるには、「どんな話を、どんな順番で、どのように伝えたらいいかな?」などと考えてみるのです。
この場合、親御さんは 一緒に宿題を見てあげながら、その都度(いちいち)、褒めたりするといいと思います。
勉強をすることで得られた快感や快楽という「成功体験」が、この先もずっとお子さんの人生に影響していきます。
ですので、その都度「お!凄い!もう1問できたの?早~い♪」「じゃ、次やってみようか!?」などと言いながら 宿題に向き合ってあげる。
そして、宿題を全てやり切ったら…
「嫌な事なのに、よく頑張ってできたね!
流石!○○は、素晴らしい!」等
このように言いながら抱きしめたり、ハイタッチしたり、大袈裟に喜んであげる。
上記のような接し方を 毎日続けていくと、宿題をやらなかったお子さんも、やる気になってくれると思います。
また、実際にこの方法で、多くのお子さんが、勉強ができるようになりました!
もちろん、親御さんは慣れるまで、大変かもしれません。
しかし、工夫して伝えることで、お子さんは改善していきますので、焦らずに一歩ずつ進めて下さいね。
最期まで お読み下さり、ありがとうございました。
まとめ
1、褒めるを意識し過ぎて、叱り方が分からなくなっていませんか?
2、怒る・叱る・注意する 3つの違いを知る。
3、褒める・叱る・注意する、伝える工夫を忘れない。
この記事の後によく読まれています

Ranking
最近の投稿